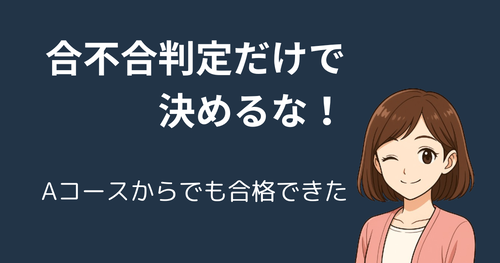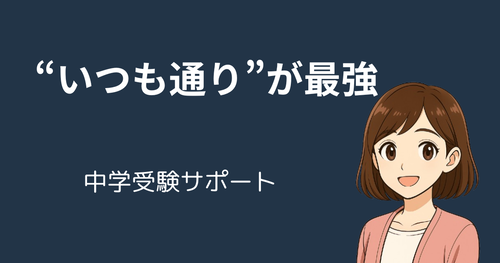この記事には広告が含まれています。
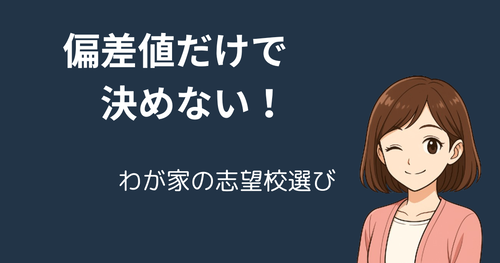
偏差値で志望校を選定するのが一般的でしょうか。なんとなく有名校だから、学校祭や説明会で実際に見聞きしたから、などと選定基準はさまざまです。
知人が通学している、あるいは親戚にOBがいる方などは、すでに志望校が決まっている場合もあるでしょう。しかし、我が家のように札幌以外で生まれ育ち、中学受験経験のない親の場合は情報収集から始めます。
今はWeb検索で簡単に学校のHPや口コミを確認することができますが、中学受験に関する雑誌もたくさん発刊されるので参考になります。
ここでは、偏差値以外の視点で志望校を選定する基準についてお伝えします。
【偏差値抜きで考える】志望校選定の3つの基準
年功序列・終身雇用の崩壊、学歴が人生を左右するという時代ではなくなりつつあります。また出る杭は打たれるという時代でもありません。
高卒でも起業して成功している人はたくさんいます。学歴は関係ない時代なのかもしれません。しかし、お子さまが目指したい将来像が明確になったときに、学力が障壁とならないために、勉強はできるに越したことはありません。
一番はお子様に合った学校を選ぶことです。
親が情報収集していくつかに絞り、学校見学などを通して子どもと決めるスタイルが多いと思います。
志望校を学校の知名度と偏差値だけで決めないと思いますが、以下の基準を参考にするとなかなか決められない方には参考になるでしょう。
志望校選定の3基準
①男女別学か共学か
②進学校か付属校か
③改革を謳う学校か否か
それぞれについて説明します。
①男女別学か共学か
これは志望校を選定する際にまず考えるところではないでしょうか。
性を意識するのは男女間だけではありません。
個人に合わせて、性を意識することなく学校生活を楽しみたい・楽しませたい、または勉強だけでは学べない「こころの成長」も重視したいなどの理由で学校を検討するのもよいでしょう。
②進学校か付属校か
進学校とは大学受験が必要な学校、付属校は大学受験をしなくても進学できる学校のことを指します。大学を受験することで視野も広がり、学力を伸ばすことができるとも考えられます。
一方、付属校であっても大学受験を選択する子も多くいます。
大学付属の中高一貫校でも高校受験をする子もいるので、進学してから再検討するのもよいかもしれません。
将来就きたい職業によっては進む方向も異なりますし、途中で進路を変更することもあります。
子どもの人生です。まだ12歳だと思っていても、もう12歳です。あと6年も経てば大人です。親が子どもの将来を決めてしまわないようにしたいものです。
③改革を謳う学校か否か
学校が改革を謳っている場合、時代に即した変化に富んだ環境と考えられます。子どもは新しいものへ適応力が高く、親にとっても我が子の未来を考えると新しいものに触れさせたいと思うものです。とても魅力的に映ります。
しかしその反面、各教員も変化を受け入れることに精一杯の可能性も考えられます。変化することは良いことかもしれませんが、安定していない時期に入学するとお子様が苦労するかもしれません。
さらに改革が立て続けに行われている場合は、実はその改革が「うまくいっていない」のが理由ということもあるかもしれません。
では、昔からの伝統を守り続ける学校のほうがよいのでしょうか。
ことばを変えれば「時代おくれ」といえるかもしれません。

じゃあどういう学校を選べばいいの? もうわからなくなってきた。
「我が子はその学校に合っているのか、楽しく学生生活を送ることができるか」という視点で志望校を選定することが一番です。

学校説明会にも学校祭にも行って確かめてきた。子どももこの学校がいいって言うし、進学したらきっと楽しいと思うんだけどな〜。

でも、学校説明会や学校祭は「よそ行き」だと感じるよ。いわば集客のためのイベントでしょ。当然いいことしか言わないしね。
当然ですよね。学校HPもいいことばかり。学校説明会で在校生の保護者が体験談を発表する場面もありますが、それも「学校の宣伝」のひとつです。
入学してから「こんなはずじゃなかった」と思うことがないように慎重に選ばなければなりません。
中学受験が東京を中心に過熱化しており、受験生よりも私立中の定員の方が少ない状況です。
公立が劣っている訳ではありません。むしろ公立のほうが一律で整備されているために「抜けがない」のです。「ハズレの私立中」も存在します。
十分に情報収集をして志望校を検討しましょう。
SSH指定、SGH指定とは
SSHはスーパーサイエンスハイスクールのこと
高等学校等において、先進的な理数教育を実施するとともに、高大接続の在り方について大学との共同研究や、国際性を育むための取組を推進します。また創造性、独創性を高める指導方法、教材の開発等の取組を実施します。
SSH指定校は受けた補助金で生徒が興味を引くような実験や取り組みを行うことが多いようです。公立学校では経験できないことができるというところは大変興味深いものです。
SSHに指定されていない「私立学校」では、学費や寄付金などで同じような取り組みを行っている場合もあるかもしれません。金銭的に余裕のあるご家庭であれば、教育費はこだわらず子どもにとって最適な取り組みを行っている学校を選定することもあるでしょう。
札幌圏でいうと、立命館慶祥中学校と札幌日本大学中学校はSSH指定校となっています。
次に「SGH」についてご紹介します。
SGHはスーパーグローバルハイスクールのこと
高等学校等におけるグローバル・リーダー育成に資する教育を通して、生徒の社会課題に対する関心と深い教養、コミュニケーション能力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、もって、将来、国際的に活躍できるグローバル・リーダーの育成を図ることを目的としています。
スーパーグローバルハイスクールの高等学校等は、目指すべきグローバル人物像を設定し、国際化を進める国内外の大学を中心に、企業、国際機関等と連携を図り、グローバルな社会課題、ビジネス課題をテーマに横断的・総合的な学習、探究的な学習を行います。
学習活動において、課題研究のテーマに関する国内外のフィールドワークを実施し、高校生自身の目で見聞を広げ、挑戦することが求められます。
指定されている学校の目指すべき人物像や具体的な課題の設定、学習内容は、地域や学校の特性を生かしたものとなっております。高等学校等において、先進的な理数教育を実施するとともに、高大接続の在り方について大学との共同研究や、国際性を育むための取組を推進します。また創造性、独創性を高める指導方法、教材の開発等の取組を実施します。
引用元:文部科学省HP
このSGHは令和2年までで終わった取り組みでした。指定されていたそれぞれの学校の成果をご覧いただきたい場合は、文部科学省のこちらのページからどうぞ。
まとめ
志望校を選定する際には、合格可能性を数値で測るテストで【偏差値】を一つの目安とする方法が一般的かと思います。学校を見学して校風を確認したり、大学進学実績も目安となるかもしれません。
本記事では、志望校選びとして一般的な偏差値以外の視点で以下の3基準をまとめました。
偏差値以外で考える志望校選定の3基準
①男女別学か共学か
②進学校か付属校か
③改革を謳う学校か否か
お子さまに合う学校を見つけられることを願っています。
にほんブログ村